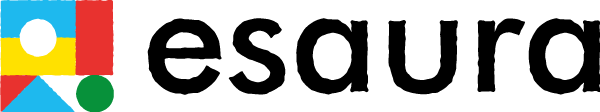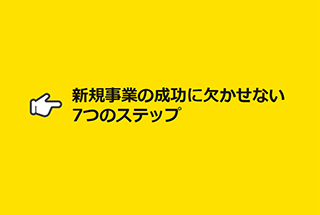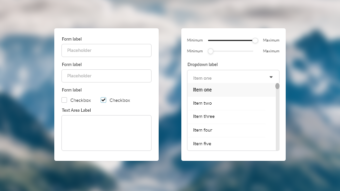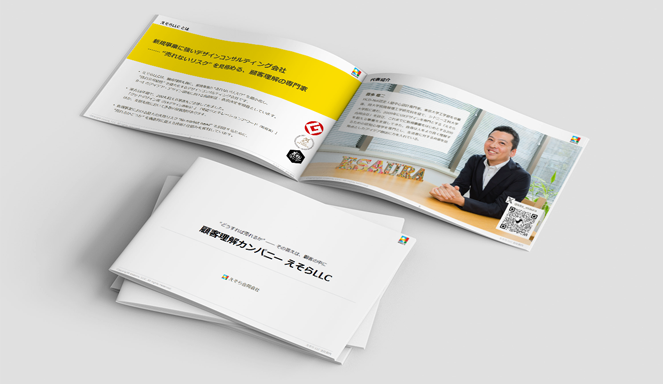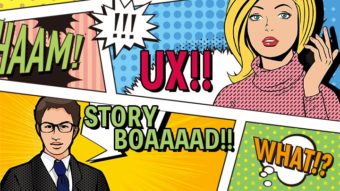日本国内の携帯キャリア大手3社の5Gサービスの提供開始をきっかけに、5Gという言葉を、CMやSNSなど様々なメディアで見聞きするようになりました。
5Gとは一体どういうものなのでしょうか。
特徴として言われているのは、「通信速度・容量の増加」「遅延の低下」「同時接続数の増加」ですが、具体的に何が変わるのかと言えば、スマホの通信速度が速くなるんだろうな~というくらいで、いまいちピンときませんね。
そんな背景の中、実際には強化された通信インフラを活用した取り組みが、さまざまな企業やスタートアップで行われています。 そこで今回は、既に走り出している活用事例をもとに、5Gが普及することで特にどのような領域で、私達の生活に変化があるのか、考えてみたいと思います。
目次
領域①:スポーツ観戦やライブなど現地参加型コンテンツ

活用事例:
- China Unicom developing 5G VR streaming tech
http://www.telecomasia.net/content/china-unicom-developing-5g-vr-streaming-tech - プロ野球を好きな角度でライブ観戦、世界初、「5G」で自由視点映像のリアルタイム配信に成功
https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20190327_01
5Gを利用することで、ドローンのようなモバイル通信を使うような機器が撮影した映像でも、リアルタイムに遅延なく配信することができるようになります。
これまでライブ配信と言えば、テレビやモニター上で見る場合が多く、実際に現地に見に行くことに対する下位互換だったと思いますが、これからは、例えば野球の試合をピッチャーとキャッチャー双方の視点で観戦したり、家にいながらアーティストの目の前で演奏を見ることができるといった、5Gを使ったライブ配信ならではの価値が提供されていくようになりそうです。
こういった現地参加型のコンテンツについては、現地に行くこと自体の価値は無くなりはしないでしょうが、参加方法は多様化し、むしろライブ配信の方で見たいといった価値観やニーズも生まれてくるのではないでしょうか。
領域②:医療や建築など現地でオペレーションが必要な領域

活用事例:
- 遠隔操作の無人建機で災害復旧! 建設業界の課題を解決する『au 5G通信』の実力:TIME&SPACE
- 5G向けボディシェアリング遠隔操作ロボットを国際ロボット展で動態展示 H2Lがドコモと共同開発:ロボスタ
5Gの遅延操作と大容量通信を活かした遠隔操作も、生活者の体験や価値観を変えるであろう注目領域のひとつです。現場の状況をリアルに把握しながら、遅延なく操作が行えるようになるため、医療や建設現場、災害復旧現場などで、より信頼性の高い遠隔技術としての活用が期待されています。
特に上記のKDDIの事例では、5Gを用いることで3D映像を扱えるようになり、作業に不可欠な距離感の把握ができるようになったことが、実用性を高めることにつながったようです。
遠隔操作により、天候等による過酷な環境での作業や、危険な場所での作業を行う必要がなくなるため、現場の方々の労働環境を改善できるだけでなく、必要な人・場所にスピーディーにサービスを届けることができるようになりそうです。
公共や社会インフラとして、私達の生活が支えてもらう上で無くてはならないものになっていきそうです。
領域③:自家用車や輸送トラックなどの自動運転

活用事例:
- 5G’s Important Role in Autonomous Car Technology:Machine Design
- 国内初、5G等を活用した複数台の遠隔監視型自動運転の実証実験の実施:KDDI IoT
以前から自動運転技術には注目が集まっています。車の自動運転には実用段階によってレベルが設定されており、システムが全ての操作を代わってくれ、完全に運転から意識を離せるレベルのものはまだ市販には至っていません(2020年4月時点)。
これを推進する技術として5Gは期待されており、特に多くの容量を遅延なく高速に通信できるようになることは、周囲の状況に応じて即座にレスポンスが必要な自動車の運転において、安全性担保のために必須と言われています。
車の運転に人の操作や判断が必要なくなれば、生活者にとっては以下のようなメリットが考えられるかもしれません。
- 車での移動時間は自由な時間となるため、例えば睡眠したり娯楽を楽しむ時間として使えるようになる
- リモートワークとの合わせ技で通勤時間をそのまま勤務時間として扱えるようになる
- 人件費のかからない無人タクシーなどの普及で、毎日座って車通勤が可能になる
また、人が運転しなくなることで免許や資格の意味も変わってきます。トラックでの輸送業務なども、積荷の管理だけを行えばよいならば、例えばトラックの免許を持っていない方が、パート業務として運送に関わるといったことができるようになるかもしれませんね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。取り上げたのはほんの一例ですが、5Gの普及は、単純にスマホの速度が速くなるだけではなく、これまで物理的制限や距離的制限によってできなかったことができるようになる可能性があるということが分かると思います。
上でとりあげたようなサービスが普及することで、生活者の日常の「当たり前」も、5Gを使った技術を基本とした体験に置き換わっていくことになります。それはつまり、生活者への共感を起点とするUXデザインにとって、見逃せない変化がすぐ近い未来にやって来ているということでもあります。
今後も5Gを活用した新たなサービスがどんどん登場してくるのだろうと思いますが、どんな未来がやってくるのか、今からとても楽しみですね。
5Gを活用して新しいサービスや価値を提供していきたいが、どう進めればいいかわからない、とお悩みの方はご相談に乗りますので、ぜひお問い合わせください。