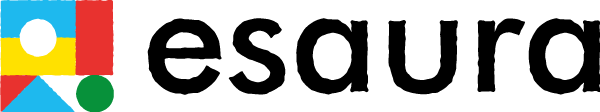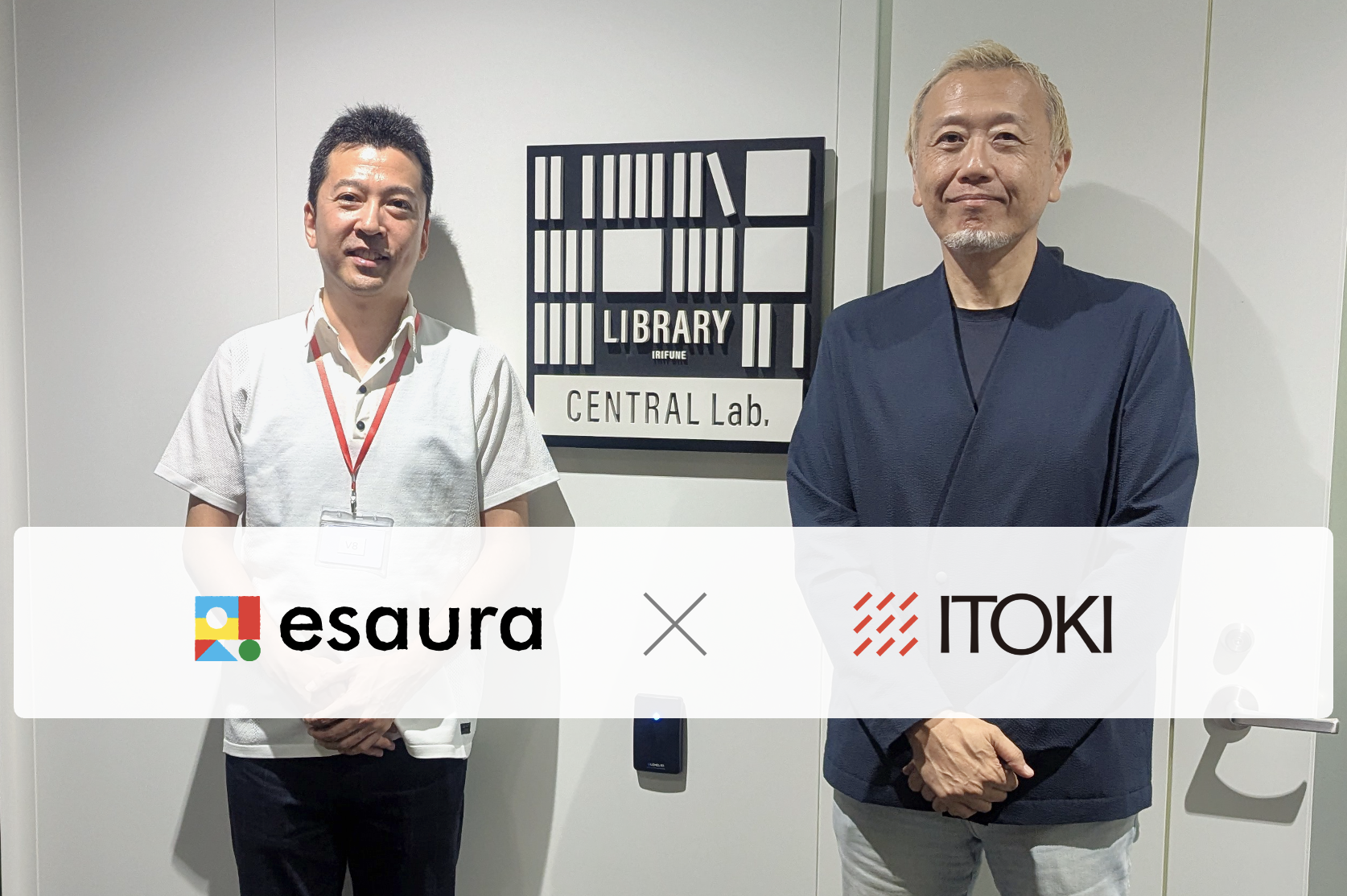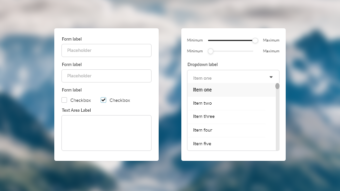今回は、株式会社イトーキ様の新規事業開発を支援した事例をご紹介します。
同社の中央研究所(CENTRAL Lab.)は、10年後のオフィスを見据えた新規事業構想を進められていましたが、「その構想が未来のユーザーに受け入れられるのか」という問いに直面していました。
そこで弊社にご相談をいただき、2024年8月から2025年7月までの11ヶ月にわたり、顧客理解を起点とした仮説検証の伴走支援を行いました。 中央研究所 所長の清水様に、その取り組みを通じて得られた気づきや成果をお話しいただきました。
| クライアント情報/ご担当者様情報 | |
|---|---|
 |
|
目次
ご依頼前の課題と成果
<背景/課題>
中央研究所(CENTRAL Lab.)は、10年先のオフィスのあり方を構想し、新規事業の可能性を探るために立ち上がった少数精鋭のチームです。未来の社会課題や技術を踏まえたアイデアを描く一方で、そのアイデアが実際にユーザーに受け入れられるのかという点を確かめる方法を模索していました。
<パートナー選定理由>
こうした課題に対し、対話を重ねながら構想そのものを一緒に磨いていけるパートナーを探されていました。その中で、対話の質が高く、壁打ち相手として率直かつ本質的な議論ができる点を高く評価いただきました。また、決まった枠組みに当てはめるのではなく、顧客理解を起点に仮説を検証し、「オフィス」という事業ドメインへの理解を前提に柔軟に進める伴走スタイルにも期待を寄せていただき、今回のご依頼に至りました。
<課題に対する成果>
伴走支援を通じて、顧客インタビューやストーリーボードを用いた仮説検証のプロセスを体系的に実践しました。その中で、当初想定していた顧客像とのギャップが明らかになり、アイデアの伝え方やターゲット像を見直すことができました。 結果として、「ニーズはゼロではない」という確信を得られたことが最大の成果でした。
プロジェクト概要
 えそら合同会社 代表社員
喜多 竜二
えそら合同会社 代表社員
喜多 竜二

インタビュー
未来のオフィスを描く中央研究所。10年先を見据えた「世界線」を探る挑戦
– はじめに、「中央研究所(CENTRAL Lab.)」について、活動内容やミッションについて教えて下さい。

清水様:当社の主たる事業は、お客様のオフィス構築と、そこで使うオフィス家具の製造販売です。 中央研究所は、オフィスとオフィス家具づくりに今後訪れる課題に長期的視点で取り組むため、2023年に新設された小規模の組織で、10年先を見据えた未来のオフィス像を描く役割を担っています。
私たちのミッションは、当社の技術と今後進展が見込まれる技術、社会課題などを掛け合わせ、「10年後にはオフィスがこうなっているかもしれない」という、起こりうる未来のシナリオを描き出すことです。 私たちはその未来のシナリオを「世界線」と呼んでいるのですが、一つの具体的な世界線を描いた上で、「このようなことが起こるならば、私たちはこういう新しい選択肢を持つべきではないか」と会社に提案していく、というのが私たちの活動です。
未来構想を“ユーザーが受け入れるか”を確かめる出発点
– 最初の接点はお問い合わせではなく、ライトにご相談いただける「カジュアル相談」からだったと思います。当時はどのようなご状況だったのでしょうか。
清水様:私たちが取り組んでいるのは、10年後のビジネスを構想することです。空想するところまではできるのですが、それがビジネスとして成り立つかのか、つまり顧客に受け入れられるのかどうかは、技術の話とはまた別の話です。技術先行で「こんなすごい技術ができました」と発表しても、うまくいかないことが多い。それは避けたかったため、ビジネス開発のサポートも同時に進めたいと思っていました。
特に、私たちが考えていたリサイクル系のアイデアは、ユーザー体験そのものです。10年後には技術だけでなくユーザーの意識も変わっているはずなので、そこを読み取らないと、現在のユーザーに話をしても表面的な理解にとどまってしまいます。どうやってアイデアを形作っていけばいいか考えあぐねていたところ、「これはユーザー体験デザインの領域じゃないかな」と思い、いくつか企業を探していた際に、えそらさんのカジュアル相談の場を見つけました。
えそら 喜多: 当時、印象的だったのが、構想されているアイデアは「理屈としては否定されることはない」が、「このサービスは現在の感覚でいうと、とても面倒であるため、本当に導入してもらえるのか」と相反する事をおっしゃっていたことです。
リサイクルというところでユーザーにちょっと負担を強いる部分もある中で、そこが本当に受け入れられるのか、というところは最初のカジュアル相談の中でおっしゃっていましたね。
清水様:私たちが取り組んでいるのは、「地球環境」のような非常に大きなテーマです。こうした大きな課題は、私たち供給側の理屈、つまり「環境に良い技術です」と提供するだけでは解決できるわけがありません。 誤解を恐れずに言うと、本気で解決を目指すなら、サービスを利用するユーザーにも、リサイクルのための分別といった相応の協力や負担をお願いする必要があると思うんです。
ただ、今のユーザーに「10年後にはこれが当たり前になりますよ」と伝えても、「そんな面倒なことまで考えていません」と感じてしまうかもしれない。その「本当に協力してもらえるのか?」というユーザーの受容性、つまり現在の価値観とのギャップを確かめることが、今回のプロジェクトの出発点でした。
壁打ち相手としてのパートナーを模索。本質を共に探れる“対話の質”が決め手
– 外部パートナーを選ぶにあたって重視したポイントはどこでしたか?
清水様:対話をしながら一緒にアイデアを練り上げていける「壁打ち相手」 が必要でした。支援いただくにしても、どのような方が当社に合っているのかもわかりかねたため、まずは直感的に3、4社の人と会話をしてみて、波長や肌合いが合うかどうかで決めようと思いました。
眼前のQCD(品質・コスト・納期)を優先しすぎると本質的な議論が後回しになってしまうことがあります。特に今回扱っているエコロジーのようなテーマは、長期の課題解決が必要なので、外形的な制約を外して本質を追求することを大事にしました。
えそら 喜多: 当時も「いつまでに決める必要がある」といったことは特におっしゃっておらず、期限を定めずにパートナーを探されていましたね。
– 何社か声をかけられていた中で、弊社を選んだ決め手はどこでしたか?
清水様: 一番の決め手は、対話の質が高く、壁打ち相手として率直かつ本質的な議論ができたことですね。先ほどもお話した通り、私たちが今回特に重視していたのは、長期的な視点で自由に発想を広げながら、本質的な部分を一緒に探っていけることだったので、決まった枠組みに当てはめて進めるのではなく、対話の中から新しい切り口を生み出していける柔軟さを求めていました。
その点、えそらさんは私たちの事業ドメインである「オフィス」という世界観に強い関心を示してくれましたし、顧客との対話を重ねながらコンセプトを固めていく自由度の高い進め方が、私たちの考えと自然にフィットしました。
えそら 喜多: 確かに、私たちの軸足はデザイン会社にあって、コンセプトを具現化するところをお手伝いしています。その中で言うと、型はありますが、基本的には「顧客と可能な限りたくさん対話しましょう」というのが私たちの型なので、対話の仕方は割と自由です。対話を繰り返す中でコンセプトを固めていく、そういった自由度みたいなところがマッチしたのかなと思いますね。
顧客インタビューで崩れた思い込み。仮説を磨き、ターゲットを絞り込む学びへ

えそら 喜多:プロジェクトの初期段階では、「このアイデアが本当に顧客に受け入れられるのか」を確かめることが大きなテーマでしたね。ただ、想定していたターゲットが既存事業のお客様とは少し異なり、社内にコネクションがない状況からのスタートでした。そこで弊社のインタビュープラットフォームpivo経由でインタビュー対象者を探し、対話の機会を作らせていただいたわけですが、そのプロセスを経て、何か気づきや変化はありましたか。
清水様: 「世の中には、本当にいろんな人がいる」と改めて痛感しましたね。私たちが「こういう課題感を持っている人と話したい」とリクエストするのは簡単ですが、その条件にぴったり合う人を10人集めること自体がまず難しい。さらに、同じような条件で集めていただいた方々でも、話してみると課題の捉え方や優先順位が全く違うんです。
当初、私たちが「こうだろう」と思っていた顧客像と、実際にうかがった生の声との間には、やはりギャップがありました。結果的に、自分たちの思い込みが崩れていく感覚があり、それが非常に良かったなと思います。
えそら 喜多:インタビューで得られた発見は、当初のアイデアを変えるほどの大きな変化だったかと思います。その点は、すんなり受け入れることができましたか。
清水様:アイデアの根幹や、成し遂げたいと思っている本質的な部分は変えていません。ただ、その価値をユーザーに届けるまでのアプローチや伝え方は、大きく見直す必要があると気づきました。「これはいけるぞ」という確信をつかみに行くプロセスが、思っていたほど簡単ではないと痛感した、という方が近いですね。
特に、1時間のオンラインインタビューという限られた時間で、まだ世にないサービスの背景や意図を正確に理解してもらうのは至難の業です。こちらが本当に知りたい核心部分をいきなり聞くのではなく、一度分解して違う角度から質問してみるなど、聞き方を工夫する必要性を強く感じました。
えそら 喜多: インタビューを繰り返す中で、インタビュー自体の精度を上げていく必要があるな、ということに気づかれたということですね。
清水様:そうですね。聞き方を工夫するのに加えて、そもそも、本当に求めているターゲットに出会える確率は低いのだという現実も痛感しました。例えば10人の方にお会いしても、「この人こそ、我々が解決したい課題をまさに抱えている」と心から思えるのは、1人いるかいないか。そういったターゲットに会える確率は、それくらいなのだな、という現実的な手応えを得ました。
えそら 喜多: それは決してネガティブな結果ではなく、むしろ大きな前進だったと思います。最初のインタビューで設定したターゲットの条件が、まだ少し広すぎたという仮説が検証できたわけです。だからこそ、次のインタビューではより条件を具体化してターゲットを絞り込む、という次の具体的なアクションが見えた瞬間でもありましたね。
清水様:おっしゃる通りです。インタビューは本当にテクニックだと思いますが、回を重ねるごとに少しずつコツがつかめてくる感覚でしたね。
ストーリーボードで見えた“社会課題と個人課題の溝”。現場で掴んだリアリティ
えそら 喜多:プロジェクトでは、アイデアを可視化するために「ストーリーボード」の作成にも取り組んでいただきました。慣れないフォーマットだったかと思いますが、いかがでしたか?
清水様:難しかったですね。あの1コマ目から4コマ目に沿って顧客の課題と解決後の姿を描く、という構造は、非常に卓越した考え方で、その通りだと思いました。その構造に当てはめようと一生懸命考えたのですが、意外とそんなに上手くいかないんです。
私たちのビジネスはオフィス空間やファシリティ全体が対象です。利害関係者も多く、BtoBならではの複雑さがある。複雑な全体像を4コマに落とし込むのは容易ではなく、どこを削ぎ落とし、どこに焦点を当てるかが問われると感じました。構想の全てを詰め込むのではなく、もっと小さなパーツに分けて考えるべきかもしれない、という気づきがありました。

えそら 喜多: おっしゃる通り、4コマという少ないコマ数で「何が一番大事なのか」を絞り込むことが、このワークのポイントでした。
今回のプロジェクトでは、御社が実現したい「解決策」はある程度定まっていたと思います。そのため、ストーリーボードを使って「では、その解決策を本当に必要としているのは、一体どんな課題を持った、どんなターゲットなのか」という、空白になっていた1コマ目と4コマ目を探す旅だったと言えますね。
– その「空白」を探す中で、どのような発見がありましたか?
清水様:一番大きな発見は、「社会全体の大きな課題」と「個人が感じる身近な課題」との差です。私たちの構想は地球環境のような「社会課題」からスタートしていますが、インタビューではそれぞれの生活範囲での会話が中心になりますので、大きな話と同時に話すのはなかなか難しいと感じました。
– インタビューの実施形式(オンライン/対面)の違いについても、多くの気づきがあったようですね。
清水様:はい。今回は特に、オンラインインタビューと、実際にオフィスに伺う対面インタビューとでは、得られる情報量が全く違うことを実感しました。
えそら 喜多:特にオフィス関連の課題は、やはり現場の「モノ」や環境を実際に見ないと分からない部分が大きいですね。
清水様:今回、訪問させていただいた2件は非常に良いインタビューになりました。ただ、これはあくまで成功例かもしれないので、この結果を基準にしすぎず、今後のインタビュー計画を立てなければならない、という冷静な視点も得られました。
責任者こそ顧客の一次情報に触れるべき。顧客の声が意思決定と社内説得の武器になる
清水様:はい。今回は特に、オンラインインタビューと、実際にオフィスに伺う対面インタビューとでは、得られる情報量が全く違うことを実感しました。
えそら 喜多:清水さんは事業開発を率いる立場でありながら、ご自身も現場で手を動かされていますよね。私たちのお客様の多くは、意思決定をする責任者と現場の担当者が分かれていることが多いのですが、清水さんのように両方を担っているのは稀なケースだと思います。裁量がある一方で、ご自身で全てを確かめなければならないプレッシャーもあるのではないでしょうか。
清水様:技術的なことは専門家に任せていますが、ビジネス面の検証や、ユーザーが本当に受け入れてくれるかを確かめることは、基本的には責任者、つまり事業を推進する当事者が自らつかみに行かない限りはダメだと思っています。どこかで「これはいけそうだ」という手応えや感触を自分で持たない限り、事業は進められないと思うんです。
ここが、スタートアップの起業家との違いかもしれません。起業家は「これをやりたい」という突き動かされるものがあって、それを自分で確かめているはずです。一方で、企業の新規事業は担当者がアイデアを出し、責任者が判断する形が多いですが、それだけでは限界があると感じています。
せっかく企業には一定のリソースがすでにあるので、そのリソースを使って責任者自らが顧客の元へ足を運ぶといった「リアリティのあること」をやった方が、事業推進においても大きな価値があると感じています。
えそら 喜多:現場の担当者の方から、「意思決定者の方に、一体何を伝えれば分かってもらえるんだろう」という悩みをよく聞きます。清水さんはその両方の立場を担っていらっしゃいますが、ご自身の経験から、意思決定の際に「この情報があったから決めやすかった」というものはありましたか。
清水様:結局のところ、一次情報を取りに行くこと以上の説得力はないのではないでしょうか。責任者になればなるほど間接的な情報しか入ってこないので、「私、10人に話を直接聞きました」という事実は、何より大きな説得力を持ちます。
それは社内を説得するためだけでなく、自分自身のためでもあります。もし自分の仮説が間違っていたとしても、一次情報があれば自分の思い込み(バイアス)を修正できる。社内で指摘を受けるよりも、直接ユーザーから「それは違いますね」と言われる方が、より本質的で価値のあるフィードバックだと感じています。
現場の方は、責任者にどう伝えればいいか悩むと思いますが、まずは責任者が「何を成し遂げたいのか」をよく聞いてみてください。判断するだけが仕事ではなく、「この立場になったからには、これを成し遂げたい」と必ず思っているはずです。
えそら 喜多:責任者は「敵」ではない、ということですね。却下する相手と捉えるのではなく、実は同じ方向を向いている仲間だと。清水様:そうですね。そういった視点を持ってみると、これまで見えていなかったところが見えてくると思います。
「ニーズはゼロではない」――確信を得られたことが最大の成果
– 今回のプロジェクトを振り返って、特に大きな収穫や成果はどのような点だったと感じていますか。
清水様:一番の収穫は、喜多さんがおっしゃっていた「ニーズはゼロではない」と自信を持てたことです。世の中のスタートアップも、多くが「ニーズが実はゼロだった(No market need)」という壁にぶつかって失敗すると聞きます。
企業で新規事業開発をしていると、つい「ニーズはゼロではないはずだ」と思いがちですが、「ゼロもあり得る」という現実を冷静に認識した上で、「それでも、私たちのアイデアのニーズはゼロではない」という確信を得られました。反省点もありますが、プロジェクトの一巡目としては、それが何よりの成果ですね。
小さな実験から広がりを目指す今後の展望
– 現在、技術的な検証を行われているフェーズに入られたかと思いますが、今後の展望についてお聞かせください。
清水様: 本格的なリリースに向けては、プロトタイプを3〜4回繰り返し、少しずつ現実に近づけていきたいと思っています。最初は限られたユーザー向けの実験的な提供から始めるかもしれませんが、そこからどう広げていくかが次の挑戦になるはずです。今後はチームの体制も強化していきたいので、新しいメンバーへのインプットとしても、今回のプロジェクトで得た学びを活かしていきたいと考えています。
貴重なお話をありがとうございました!
えそらLLCでは、新規事業における伴走支援を行なっております。顧客理解をベースとした新規事業開発にご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。