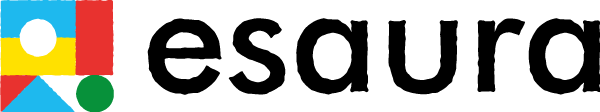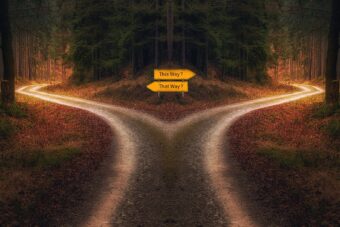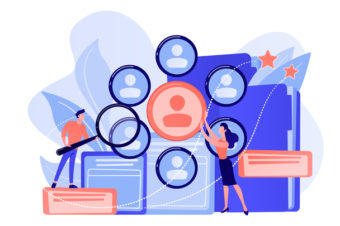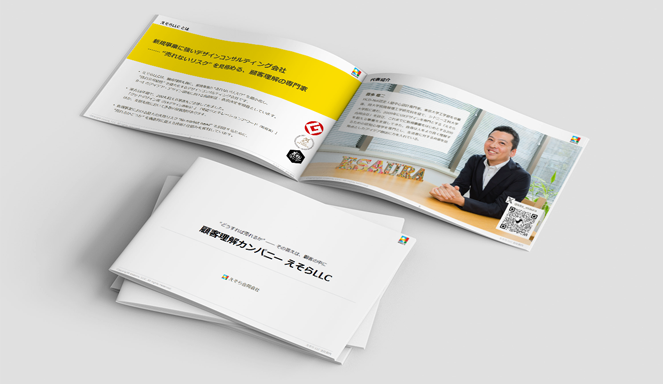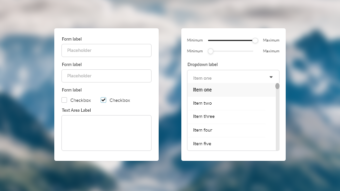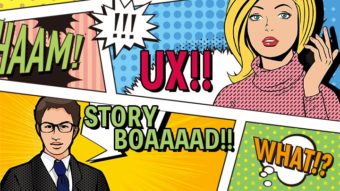ユーザーインタビューの実施経験が浅いころは、ユーザーから十分に話を深堀りすることができなかったり、正しい改善につながらないインタビューを行ってしまったりと、悩みを持つ方も少なくありません。
今回の記事では、リサーチに強いUXデザイン会社の現役リサーチャーが実践している、知っているとあなたの武器になる、ユーザーインタビューのテクニックをご紹介します。
目次
ユーザーインタビューとは
一般的にユーザーインタビューとは、「調査目的の対象となる領域にいる生活者との対話を通じて、その人の考え方や行動を理解する」手法を指します。
事業開発においては
- アイデアやデザインの種となる仮説を生み出すため
- アイデアやデザインを検証・改善するため
という2つの目的で使われます。
ユーザーインタビューの成功基準は「ユーザーの頭の中を手に取るように理解できるようになったか」
ユーザーインタビューでは、ユーザーが「なぜ」その思いに至ったのかまでを深く理解していく必要があります。そのためには、「ユーザーの頭の中を手に取るように理解できているかどうか」を一つの判断基準としましょう。
一つ例を出します。
とある母親が、子供を私立少学校に入れたい、という意見を持っていたとします。
なぜ私立小学校へ入れたいのですか?と聞くと、「子供を将来、海外でも活躍できるような人材に育てたいと考えたときに、英語教育などに手厚そうな私立校が良いと思ったから」という回答でした。
一見それらしい回答で、この母親のことを理解した気になりますが、実はこれでは足りません。英語教育を手厚くしたいのであれば、私立校だけでなく、海外留学や英語の塾に通わせることも選択肢に入ってきそうです。つまり、今の状態では、なぜ「私立小学校」にしようという結論に至ったのか、説明しきれていないのです。
この母親に質問を続けてみると、「予算の問題、離れて生活したくない、近所のママ友からの意見」という背景が出てきました。
そして、さらに深掘りを続けていくと、私立小学校でなければいけないということではなく、「近隣のインターナショナルスクールでも良い」ということだったのです。
結果として、私立小学校という分類だけではなく「予算内に収まる学校、家から通える範囲の学校、ママ友から評判の良い学校」という目線での考え方も必要ということがわかりました。
ここまで深掘りできて初めて、ユーザーの頭の中を手に取るように理解できたといえる状態になります。
ユーザーインタビューで使えるテクニック11選
では早速、ユーザーインタビューを成功させるために現役リサーチャーが実践している、おすすめのテクニックをいくつかご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
1. ウォームアップ用の軽い質問から始める
初対面の人と話をする場合、緊張から思ったように発言してもらえない可能性があります。
そこで、ユーザーが答えやすい軽い質問から始めることで、対話の雰囲気を和らげ、コミュニケーションを円滑に進めていくことができます。
具体的な質問の例として、「お仕事は何をされていますか?」「ご家族は何人ですか?」など、ユーザーの属性の確認も兼ねた質問をフレンドリーな雰囲気で始めることをおすすめします。
そうすることで、事前に取得しているユーザー情報に、万が一相違があった場合も、それを踏まえてインタビューを進めることができるため、インタビュアーにとっても役立つテクニックです。
2. 正解、不正解はないことを伝えておく
ユーザーがインタビューに回答する際、正解か不正解かのような考え方に立つと、ユーザー自身の感じたことや経験を言い変えてしまう可能性があります。
そこで事前に「ネガティブなことでもポジティブなことでも、○○さんが感じたことを率直にお話いただけることが、一番ありがたいので、遠慮なくお話いただけると嬉しいです」などと伝えておくことをおすすめします。
この人には何を話しても大丈夫なんだ、という安心感のもと、ストレスなく自由に話してもらうことで、貴重な気づきやより深いフィードバックを得ることができるでしょう
3. 対象者に対する自分の先入観(確証バイアス)を取り除く
私たちは無意識に、自分の先入観に基づいて回答を予測してしまいがちです。そのため、自分の想像力が及ばない部分については質問をすることが難しくなります。インタビュアーは、偏見のない視点で質問できるように心掛けることが重要です。
ユーザーインタビューで特に注意しなくてはならない、この “自分の先入観”のことを専門用語では「確証バイアス」と呼びます 。「A型は几帳面」「男性は力持ち」「高齢者はPCが苦手」などがわかりやすい確証バイアスの例です。
この確証バイアスの罠にハマると、つい自分の都合の良い流れに沿ったインタビューをしてしまったり、「ほらやっぱりそうだ」「そう答えると思った」と、自分の仮説を肯定する回答を意識的に拾いやすくなり、そうではない回答は軽視してしまったりなど、正しい判断ができなくなってしまいます。
とはいえ、バイアスを完全に取り除くことは不可能ですので、対策をすることがとても重要です。
おすすめは、自分の都合の良い情報だけをピックアップしてしまわないように、ユーザーの回答は偏りなくメモにとるようにすることです。そうすることで、その場では気がつけなかった大切な情報の取りこぼしを防ぐことができます。
4. オーバーリアクションで、ユーザーの話を真剣に聞いている姿勢をみせる
ユーザーに気持ちよく話してもらうためのテクニックです。
会話中に相手が大きく頷いてくれたり、理解してくれている様子が分かったりすると、安心して話すことができますよね。
そこで、ユーザーが話している内容に対して、言葉の他に表情やボディランゲージなども加え、ユーザーにわかりやすく感情を伝えましょう。特にオンラインインタビューの場合は、リアクションが伝わりづらいため、笑顔やオーバーリアクションを心がけることが大切です。
「あなたの話を真剣に聞いていますよ」という姿勢を見せることで、信頼関係が生まれ、ユーザーは自分の感じたことをより深く掘り下げ、より多くの情報を提供してくれるようになるでしょう。
5. 沈黙をコントロールする
沈黙は、気まずいと感じるものではありますが、ユーザーが回答を考えている時間です。
途中で質問を挟んでしまうことで、ユーザーが思考を停止させてしまう可能性があるため、沈黙を無理になくさないように心がけます。たとえ気まずくとも、1分待ってみましょう。
6. 未来ではなく、過去についての質問をする
未来に対しての仮定の質問ではなく、ユーザーの過去の経験や行動について質問をしましょう。過去についての質問は、ユーザーの意思決定や行動の背後にある要因や背景を探るのにとても役立ちます。
また、過去の状況や経験を把握することで、ユーザーが現在どのような状況にあり、どのような思いを持っているのかをより詳細に理解することができるでしょう。
7. オープンクエスチョンを優先する
ユーザーからより多くの情報を引き出せるように、回答範囲に制限を持たせないオープンクエスチョンを優先して使いましょう。
「昨日のご飯はおいしかったですか?」というYes・Noで回答できる質問ではなく、「昨日のご飯はどうでしたか?」といった、自由に回答できる質問をすることで、質問攻めをしなくても、ユーザーから多くの情報を引き出すことができます。
また、オープンクエスチョンを行うことで、その回答に対して深掘りをしたり、別の質問へ発展したりと、会話を広げやすくもなりますし、こちらの想定していなかった情報まで引き出せる可能性もあります。
8. 回答に対して、ストーリーを引き出す
質問に対して、エピソードを詳細に語れる人は多くありません。
例えば、引っ越しについてのインタビューで、「なぜ引っ越しをしたのですか?」とただ聞くのではなく、「どのようなきっかけがあったのですか?」「他に、どのような選択肢がありましたか?」「他の選択肢を選ばなかった理由はなぜですか?」など、なるべくいくつもの角度から質問をするように心がけると、ストーリーを引き出しやすくなるでしょう。
9. なぜを積み重ねて、具体的な回答を把握する
消費者の潜在的なニーズやモチベーションを明らかにするための質問手法に「ラダリング法」があります。この手法は、消費者の意識や行動の背後にある深層心理を理解するために使用されます。
具体的には「なぜ」を重ね、はしご(ladder/ラダー)を上っていくように、どんどん深堀りしながら繰り返し質問をおこなっていきます。
例えば
↓なぜコーヒーを飲みたいと思ったのですか?
「眠気をしっかり覚ましたいからです。」
↓なぜ眠気を覚ましたいと感じたのですか?
「集中力を高めたいからです。」
↓なぜ集中力を高める必要があるのですか?
「今日は大事なプレゼンテーションがあり、仕事での成果を出すためには集中力が必要だからです。」
このように、質問を重ねることで「コーヒーを飲みたい」という表面的な回答から、目覚める必要や集中力の向上といった、回答者の内面にあるニーズや動機を明らかにすることができます。
10. 選択や意思決定の背景を把握する
ユーザーの選択や意思決定には、その背後に必ず何らかの理由や基準が存在します。インタビューでは、この理由や基準に注目しましょう。
「他にどんな選択肢があったのか」「その中でなぜそれを選んだのか」「どのような比較をしたのか」「どんな葛藤があったのか」などについて尋ねることで、その選択に至った背景や期待値を把握することができます。
これにより、表面的ではないニーズの理解を行うことができ、適切な改善策を検討することに繋がります。
11. ユーザーの発言を正確に理解する
言い間違いや表現の解釈のゆれによって誤解が生じることを防ぐために、聞いた内容を自分の言葉で要約し、確認することはとても有効なテクニックです。
ユーザーに対して「私が理解した内容はこうですが、合っていますか?」と確認することで、共通の理解を確立し、万が一誤解があった場合も、きちんと解消した上でインタビューを進めていくことができます。
まとめ
本記事では、現役リサーチャーが実践しているユーザーインタビューのテクニックについてご紹介しました。
いくつかのテクニックを組み合わせることで、ユーザーインタビューで引き出せる情報量が大きく変わってくるはずです。
ぜひ今回ご紹介したテクニックをご活用いただき、インタビューを成功させてください!
えそらLLCでは、あなたが持っている顧客リストに直接インタビューできる仕組みを提供する、「インタビュープラットフォーム」を提供しています。日程調整や謝礼支払いなどインタビューに関わる事務工数に課題がある方は、ぜひご活用ください。